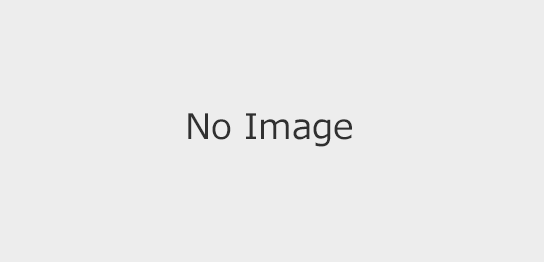Saasのアカウントの申請窓口を作るときに考えたほうがよいチェックポイント
【想定読者】 上場企業の社内情シス・コーポレートエンジニア 規模拡大に伴いヘルプデスクを仕組みを構築しようとしている人 スタートアップの社内ITの仕組みを作ろうとしている人 Saasのアカウント発行申請については、ベンチャーと作り方のポイント違いがあります。 スタートアップの規模だとslackの特定のチャンネルで以来のメンションをつけるだけで受け付けていたり、botが自動で発行してくれる自動化を作っていたりする会社もあると思います。 規模の拡大に伴い、その利用用途が掴めなくなってしまったり、解約や棚卸しを踏まえた申請情報のとり方が必要になるため、そのポイントを書きました 利用目的(その他に自由記述含む) 属性情報 オーナーチーム 棚卸しルール それぞれ説明します。 ツールの利用目的 同じツールでも、利用用途は職種によって様々です。 類似する新しいツールが出てきたり、既存のツールの機能追加によって利用用途の見直しが発生して、ツールを解約したときに、この項目を精緻に集めていることでどれくらいの影響があるのかがわかります。 また、申請の対応者は派遣社員など定型的な業務しかできないケースもあるので代替ツールの提案は難しいにしても、正社員が過去の申請を見て特殊かつ代替可能なものは提案したりすることもできるでしょう。 例えば、slackのアカウントの発行申請の用途が、「zapier で権限をそのアカウントに紐付けて特定のチャンネルに通知するため」だった場合、webhookを使えばそのアカウント発行は不要なのではないか?と提案したりすることができるわけです。 属性情報 所属チームやカンパニー情報は入れておくのが理想的です。 ツールの解約時や、休眠アカウントが出た時に確認する窓口になります。また、エンドユーザーが社外パートナーの場合もそれが分かるようにできたりします。 アカウント発行時に、プロフィールを所属チームを入れて欲しいというニーズが出たりします。そのニーズが発生した時に、過去分をまとめて更新しようというニーズに対応できます。 オーナーチーム こちらのオーナーチームは利用しているチームまたはマネージャーにするのが良いかと思います。 オーナーチームにした場合チームの統合で消えてしまうリスク、マネージャーにした場合は退職やポジション変更の可能性があり、ご自身の事業特性によってどちらの方を取るかを判断してください。 棚卸しルール 例えば月額で課金が発生する場合、30日以上ログインしていない場合 「監査対応などでそもそも90日おきしか利用ニーズが発生しない」などのケースは、その監査のたびにアカウントを申請してもらうことを握っておきましょう。 Yoshio Kimura早稲田大学人間科学部情報科卒業。 (株)すららネットにてアジア向け算数デジタル教材の開発を経て、デジタルハリウッドのエンジニア養成学校G’s ACADEMYでプログラミング講座の新規立ち上げ、営業、教育を担当。3年半に渡り、中高大学生から社会人まで計6講座500名以上へプログラミングを教える。フリーランスエンジニアを経た後、現在は(株)メルカリのコーポレートエンジニアリング部に所属。Udemyにて2つのGoogle Apps Script講座を立ち上げ、1年半で登録者数は6000人を突破。 中高英語科教員免許保有 / IPA未踏アドバンスト’18 採択者。